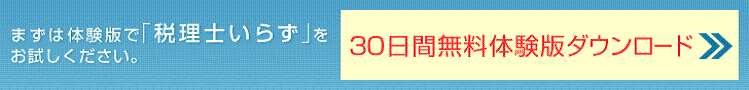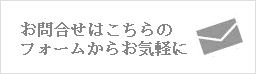|
「税理士いらず」をご利用になるのに適している法人とは?
|
|
|
「税理士いらず」は、複雑な取引のない小規模法人様を念頭に開発されました。
|
|
しかし、複雑な取引といっても、どこからが複雑になるかという線引きがあいまいです。
|
|
ここでは、どのような法人様であれば「税理士いらず」を安心してご利用になれるかという目安をご説明します。
|
|
なお、ここでご説明している事柄は、あくまでも、一定の目安になりますので、具体的には体験版を実際に
|
|
お試しになってから、ご判断ください。
|
|
また、以下のご説明では、税務申告知識にあまり詳しくない方を対象に、分かりやすさに重点をおいて
|
|
ご説明していますので、一部、正確性に欠ける部分があることをご留意ください。
|
|
|
※一定の税務申告書記載知識をお持ちの方であれば、以下の目安にあてはまらなくても、
|
|
申告書記載項目などを適便、修正することにより、ご利用になることもできます。
|
|
※具体的なケースについての導入方法については、導入ご相談事例集 も合わせてご参考ください。
|
|
|
●「税理士いらず」をご利用になるためのチェック項目
|
|
| ●
資本金1億円以下で、事業所は1つだけ
|
| ●
複雑な申告調整がない
|
| ●
消費税は税込み経理で処理している
|
| ●
その他の留意事項
|
|
 |
|
資本金1億円以下で、事業所は1つだけ
|
|
|
「税理士いらず」は、複雑な取引のない小規模法人事業者を念頭に開発されました。
|
|
資本金1億円以下の中小法人で、かつ、分割法人でない ことをご利用の前提としています。
|
|
分割法人とは、支店等が存在するために、複数の自治体に地方税申告書を提出すべき法人であって、
|
|
本店移転により、2ヶ所の自治体に地方税申告書を提出するケースについては、機能サポートされています。
|
|
 |
|
複雑な申告調整がない
|
|
|
申告調整とは、確定決算書により算出された当期利益をベースとして、各種の損金不算入や損金算入などの処理を経て、
|
|
法人税の算定基準となる所得金額を算出するための加算と減算です。
|
|
たとえば、決算書上で費用として計上された法人税は、税務上は損金となりませんので、申告調整により、
|
|
損金不算入処理(当期利益に加算)をして、所得金額を算出しなくてはなりません。
|
|
|
|
法人の税務申告処理では、申告調整は法人税別表四で、決算書の税引き後当期利益からスタートして、
|
|
以下の算式で所得金額が算出されます。
|
|
(税引き後)当期利益 + 加算項目 − 減算項目 = 所得金額
|
|
この算式での加算項目の一例としては、たとえば、交際費の損金不算入額などがあり、減算項目の一例としては、
|
|
繰越欠損金の当期控除額などがあります。
|
|
|
「税理士いらず」では、一般的な小規模法人様が必要とする以下の申告調整項目(加算項目、減算項目)のみを
|
|
限定的にサポートしています。
|
|
|
損金不算入(当期利益に加算処理)
|
|
・当期決算で計上された納税充当金(法人税、地方税、事業税)
|
|
(損金経理を選択した場合は、当期中に納付した法人税および地方税)
|
|
・交際費の損金不算入
|
|
・寄附金の損金不算入
|
|
・法人税額から控除される所得税額
|
|
|
損金算入(当期利益から減算処理)
|
|
・(納税充当金計上処理を選択した場合に)当期中に納付した前期事業税および当期事業税の中間納付
|
|
・繰越欠損金の控除
|
|
|
上記以外の申告調整が必要な場合には、申告調整処理の最後の所得の算出フェーズで、法人税別表四を
|
|
直接、マニュアル修正することができます。
|
|
 |
|
消費税は税込み経理で処理している
|
|
|
消費税の経理処理には、「税抜き経理」と「税込み経理」があります。
|
|
「税抜き経理」は、たとえば、課税売上の場合に、本来の売上高と、その消費税分について、別々の仕訳を作成します。
|
|
「税込み経理」の場合は、「売上高+その消費税分」を売上高として計上します。
|
|
旅費交通費などの費用についても同様です。
|
|
|
多くの市販会計ソフトは、「税抜き経理」と「税込み経理」の両方をサポートしていますが、「税理士いらず」は、
|
|
小規模法人を念頭に、あえて「税込み経理」のみのサポートとしました。
|
|
ただし、消費税額については、1つ1つの仕訳毎の課税区分を参照して計算しますので、正確に計算されます。
|
|
|
もし、前期まで税抜き経理を採用していて、当期から税込み経理に変更する場合は、導入ご相談事例集ページをご参考ください。
|
|
なお、新設法人(1期目)の場合は、最初から「税込み経理」を採用することになりますので、このことを考慮する
|
|
必要はありません。
|
|
 |
|
その他の留意事項
|
|
|
その他に「税理士いらず」をご利用になるのに適している法人の要件としては、以下のような項目があります。
|
|
|
・1日あたりの仕訳数は500件以下で、1決算期あたりの仕訳数は8万件以下
|
|
・消費税の簡易課税事業者の場合、事業区分は1種類のみ
|
|
・減価償却すべき固定資産は、定額法(別表十六(一)、定率法(別表十六(二)は、各50件以下
|
|
・減価償却すべき繰延資産(別表十六(六)は、25件以下
|
|
・利益の配当が発生しない
|
|
|
|